 |
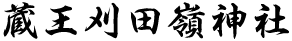
(ざおうかったみねじんじゃ) |
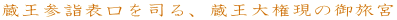 |
|
 |
|
遠刈田温泉街に鎮座する。古式にならい、蔵王登山の前にお参りしてはいかが? |
|
 |
|
境内の六地蔵。苔むした風情に時代を感じる |
|
 |
|
蔵王参詣者によって建立奉納された碑も多い |
蔵王刈田嶺神社は、願行寺(がんぎょうじ)四十八坊の一つ、嶽之坊(だけのぼう)を前身とする神社です。
嶽之坊は金峯山蔵王寺(きんぷせんざおうじ)と号し、蔵王山頂に鎮座する蔵王大権現社を司っていました。また、雪深い蔵王山は冬の参詣ができないため、例年、十月八日から翌四月八日までは御神体を遠刈田の蔵王大権現御旅宮(おかりのみや)に遷したのですが、この御旅宮は嶽之坊と同一の場所にあるなど、古くから嶽之坊と蔵王大権現社とは、同体ともいえるほど深くつながっていたのです。嶽之坊はまた、蔵王参詣表口(ざおうさんけいおもてぐち)も司っており、御山詣りが流行した江戸後期以降は、多くの参詣者を山頂の蔵王大権現へと導く役を担いました。
明治2(1869)年(※)、神仏分離令の影響を受けて嶽之坊と蔵王大権現社とは合一し、水分神社(みくまりじんじゃ)となりました。さらに、明治8年に蔵王刈田嶺神社と改めて今日に至ります。
遠刈田温泉が発展する契機となった蔵王参詣の流行。それを司ってきたこの神社は、まさに地域の歴史の中心といえるのです。
|
※記述に誤りがありましたので下記の通り訂正します(2013.10.8)。
本文中(※)部分 誤:明治5(1872)年 正:明治2(1869)年 |
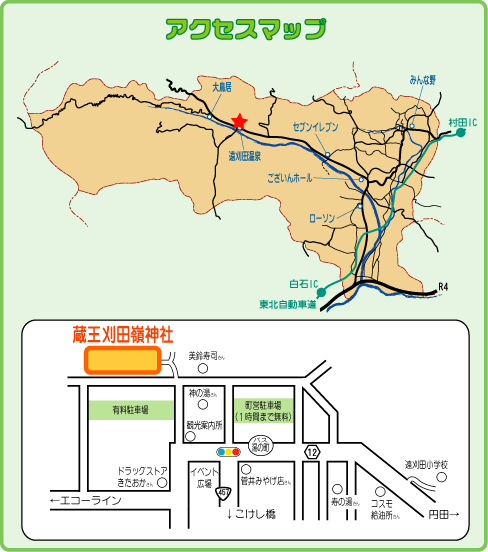 |
| 所在地 |
蔵王町遠刈田温泉仲町1 |
| 所有者 |
蔵王刈田嶺神社 |
| 公開日 |
いつでも |
| 料 金 |
無料 |
| アクセス |
ミヤコーバス「遠刈田温泉湯の町」停留所から徒歩1分 |
| 駐車場 |
なし(温泉街にある有料駐車場等をご利用下さい) |
| 現地までの案内表示 |
なし |
| 現地での説明表示物 |
なし |
| 見学のための手続き |
神社の方に一声かけてからご見学下さい。
事前の予約は不要です。 |
| 見学地の整備状態 |
良好 |
|