| や ち い せ き |
|
|
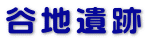 |
|
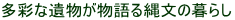 |
|
 |
| 谷地遺跡で出土した縄文土器(縄文時代中期前半) |
 |
| 石で作られたさまざまな形の道具(石器) |
本遺跡は、松川の左岸に形成された矢附(やづき)段丘面上に立地しています。平成23・24年度に行なった消防庁舎建設計画に伴う発掘調査の結果、縄文時代中期前半(約5,500〜5,000年前)の大規模な集落跡であることが判明しました。
発見された遺構には、住居跡14軒、貯蔵穴(ちょぞうけつ)55基、土器埋設遺構12基のほか、広範囲に分布する遺物包含層(捨て場遺構)などがあります。住居跡は円形の竪穴住居と、長楕円形の平地住居が見られます。地面を三角フラスコ形に掘った貯蔵穴は地上より温度や湿度の変化が少なく、害虫の侵入も抑制できるので、縄文人の主食であるドングリやトチといった堅果類などの食料を保存する施設であったと考えられます。
 |
 |
| 発掘調査の様子(手前の円形の窪みが竪穴住居跡) |
穴の中に埋められていた土器(土器埋設遺構) |
 |
 |
| 竪穴住居跡(人の立っているところが柱穴) |
食料などを貯蔵した穴(フラスコ状土坑) |
使われなくなった住居や貯蔵穴を覆うように広がる捨て場遺構などからは、推計重量10トンに及ぶ極めて多量の縄文土器・石器類が出土しました。縄文土器は主に東北地方南部地域に分布する「大木7b・8a式」に属し、大型の波状口縁や立体的な橋状把手(とって)が特徴です。また、関東地方の「五領ヶ台式」、「阿玉台式」などに由来する土器も見られ、当時の人びとの交流の実態を知ることができます。
本遺跡を特徴づける遺物として、140点を超える土偶があります。土偶の多くは妊婦を象っており、安産や子孫繁栄から転じてムラの繁栄、豊穣、豊猟への祈りが込められたと考えられています。このほか、新潟県糸魚川産の硬玉(翡翠・ひすい)製垂飾品(ペンダント)をはじめ各種の石製品、土製品が出土しています。これらの多くは具体的な用途が不明ですが、装飾品あるいは祈りの儀式に関わる器物と考えられ、捨て場遺構が様々な「もの」に宿る魂を神の世界へ帰す「もの送り」の場でもあったことを示しています。
|
 |
| 大小さまざまな土偶。多量に出土しましたが、すべて破片で完全な形を留めたものはありません。 |
 |
| アクセサリーや祈りの道具と考えられる遺物。 |
このように、本遺跡は縄文時代中期の蔵王東麓における拠点的集落のひとつと考えられ、郷土蔵王に暮らした当時の人びとの生活文化の移り変わりや、精神文化の実態を具体的に知ることのできる貴重な文化遺産です。 |
 |
|
 |
|
 |
| 所在地 |
: |
蔵王町大字円田字谷地 |
| 時代 |
: |
縄文時代中期前半(約5,500〜5,000年前) |
| 種類 |
: |
集落跡 |
| 遺構 |
: |
竪穴住居跡、貯蔵穴、配石遺構など |
| 遺物 |
: |
縄文土器(大木7a・7b・8a式)、石器、土偶、石製品、石棒など |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
・ |
白石消防署蔵王出張所と果樹園のある一帯が遺跡です。 |
|
・ |
現地には説明看板を設置しています(県道沿い消防署敷地内)。 |
|
・ |
遺跡の現状は宅地・果樹園です(発掘調査をした場所は消防署になっています)。 |
|
|
 |
|
 |
|
|