 |
 |
 |
 |
|
 |
話し手
編 集 |
:
: |
加川清八(蔵王町向山区)
蔵王町教育委員会(2010) |
|
向山の、谷地畑(やちはた)と二渡(にわたし)と前山(まえやま)と原前(はらまえ)っていう土地の寄り合った所に、ブナ堂さんのほこらがあったんだ。
ブナ堂さんのほこらには、こんな話が伝わっているんだ。
むかし、むかし、大昔。ブナ堂さんのほこらのある所には、ブナの大木があったんだ。
村の人たちはこのブナの大木を、神様の木だって大切にしていたんだ。
大地に根っこを下ろして、朝日に映えたり、夕日に染まったりする姿は、そりゃあ見事なものだったんだと。
そのブナの大木は、十抱えもある太い幹から、生い茂った枝葉を一里四方さ伸ばしていたんだと。
そのせいで、ひと山さきの松原(まつばら)のあたりでも年中日陰になっていたんだと。
ある夏の晩方、村のみんなが寄り合いをしたんだ。
「困ったなや。ブナの木の日陰はアワやキビが育たねえ。子供や孫が増えだつうのに・・・」
「んだな。伐り倒して畑にすっぺや。」
「んでも、ありゃあ神様の木だ。バチ当だんねぇがな?」
となったが、子どもや孫を食わせてゆくには、それも仕方ないべとなったんだと。
いよいよ、ブナの大木を伐り倒す日だ。きこりが八人がかりで斧を振り上げて、伐り始めたんだと。
んでも、千年を経た木の幹は石みたいに固くて、斧をはね返しちまうほどだったんだ。
それに何としたことか、やっと削った木っ端も、地面に落ちたと思ったらパッパッと舞い上がって伐り口にくっついちまって、すぐに元通りになってしまっったんだ。誰がやっても、何度やっても同じだったど。
なんとも不思議なこのありさまに、みんなは口を開けたきりで、その日はこの大木を切り倒せねがったど。
(後編につづく)
|
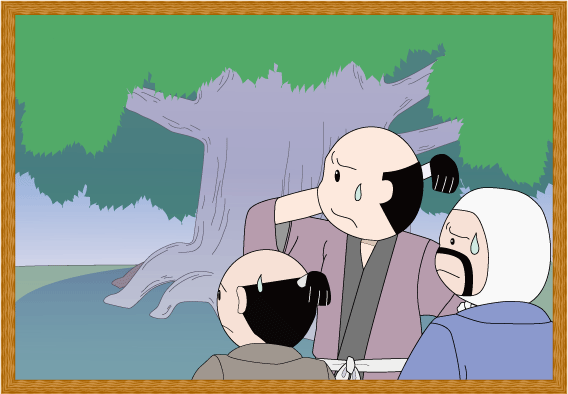 |
※「蔵王町史 民俗生活編」掲載の「ブナ堂さん(話し手:加川清八さん)」に基づき、その内容・意味・趣旨に変更を加えることなく、文体修正・一部文章修正を行いました。
|
| 2010.7.6更新 |
 |
 |
 |